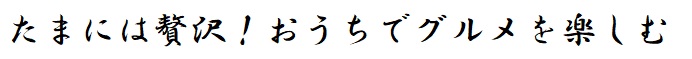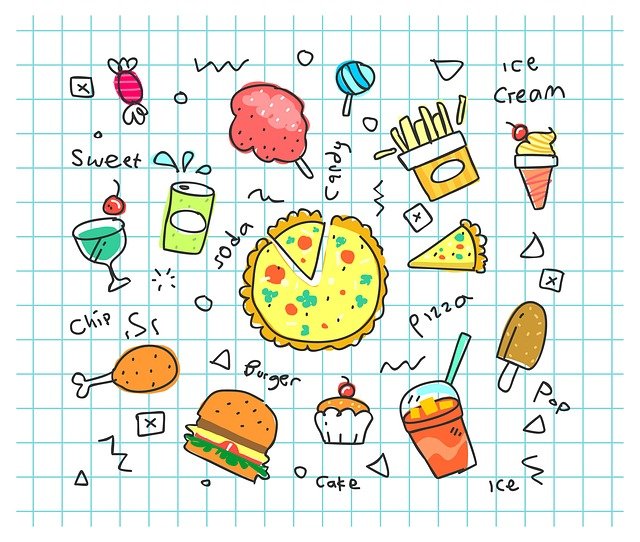
私たちは、日々多くの食べ物を摂取しています。多くの食品を気軽に選べる今だからこそ、気になるのが食べ合わせについてです。
「一緒に食べると良くない」と言われつつも、その理由がわからないケースや、意識しないままついやってしまっている組み合わせもあるのではないでしょうか。
このコラムでは、食べ合わせについての本当のところを詳しく解説していきます。「一緒に食べていいんだっけ?」と悩んだときには、ぜひ参考にしてみてください。
「食べ合わせが悪い」とはどういうこと?
食べ合わせとは、複数の食べ物を同時に食べることを言います。つまり、同時に食べた食材の相性が悪ければ、「食べ合わせが悪い」ということになるのです。
食べ合わせが悪い食材の組み合わせについては、古い時代から続く、言い伝えのようなものも少なくありません。現代を生きる私たちにとって、「いったいなぜ?」と思う機会が多いのも、このためなのでしょう。古い時代に食べ合わせが重視されていたのは、以下のような理由のためだとも言われています。
- 体の冷え予防
- ぜいたく予防
- 食べ過ぎ予防
- 食あたり予防
食べ物が不十分な時代に、つい食べ過ぎてしまうような組み合わせは好ましくありません。また、食べ過ぎや身体の冷えが原因で体調を崩したところで、今よりもできる治療は限られていたでしょう。
傷みやすい食材に、匂いが強い食材を組み合わせてしまうと、その変化がわからないという恐れもあります。このように、さまざまなリスクを低下させるために、食べ合わせに関する考え方が広く浸透していったのではないでしょうか。
「食べ合わせが悪い」に潜む誤解
食物や栄養、そして人体に関する研究が進んだ今、食べ合わせについても、さまざまな新事実が明らかになってきています。これまで「食べ合わせが悪い」とされ、敬遠されてきたものの、実際にはそうでもないとわかっているものもあります。
「食べ合わせが悪い」と誤解されているのは、以下のような組み合わせです。
- うなぎと梅干し
- 天ぷらとすいか
- カニと柿
うなぎと梅干しは、食べ合わせが悪い例として有名なもの。しかし実際には、脂の乗ったうなぎと、さっぱりとした梅干しの相性は決して悪くないのです。梅干しを食べることで、口直しや食欲促進のほか、消化を良くする効果も期待できると言われています。ただし、脂っぽいものも酸味の強いものも、刺激が強いのは事実。胃腸が弱っているときには、一緒に食べるのは避けた方が良いかもしれません。
天ぷらとすいかも有名ですが、実はこちらにも、科学的根拠はありません。もちろん食べ過ぎは良くありませんが、天ぷらそばを食べたあとのデザートにすいかを食べたからと言って、栄養面では何ら問題はないのです。
カニと柿については、中国で古くから伝えられている食べ合わせの一つ。どちらも身体を冷やしやすい食材ではありますが、栄養面での問題はありません。昔は流通経路が確保されておらず、「海のもの(カニ)と山のもの(柿)を同時に食べると、どちらが傷んでいる可能性がある」という理由もあったようです。海のものも山のものも素早く流通させられるようになった現代においては、組み合わせに問題はないでしょう。ただ、普段から身体が冷えやすい方は、「カニは鍋でいただく」など体を冷やさない工夫をした方が良いかもしれません。
本当に食べ合わせの悪い食品は?
単なる言い伝えと捉えがちな、食べ合わせについて。しかし実際には、本当に身体に負担を与えてしまう可能性がある、食べ合わせが悪い組み合わせも存在しています。
いくつかのパターン別に紹介するので、参考にしてみてください。
★胃腸に負担をかける
食べ物の組み合わせによっては、胃腸への負担が大きくなってしまいます。感じ方には個人差がありますが、胃腸が弱っているときには避けた方が良いでしょう。
- ラーメン×ごはん
- うなぎと桃
ラーメンとごはんのように、炭水化物同士を組み合わせると、ビタミンB1不足がエネルギー循環を滞らせてしまう可能性があります。結果として、太りやすくなったり疲れやすくなったりするので、注意しましょう。
また、うなぎとの食べ合わせに注意したいのは桃です。桃に含まれる成分によって、うなぎに含まれる豊富な脂肪分の分解が阻害されてしまう可能性があります。
★有害な物質を生成してしまう可能性がある
食べ物同士の組み合わせによっては、人体にとって有害な物質を生成するケースがあります。
- 焼き魚×漬け物
- ほうれん草×ベーコン
- 輸入レモンと紅茶(コーヒー)
これらの組み合わせにおいては、それぞれに含まれる成分が反応し、発がん性物質が生成される可能性があります。
輸入レモンと紅茶(コーヒー)の組み合わせに注意が必要なのは、レモンに防カビ剤が使われている恐れがあるためです。国内産のレモンなら、安心して使用できます。
また、発がん性物質が生成されたからといって、すぐにがんになるわけではありません。適正量を摂取するだけなら、病気リスクは極めて低いと言われていますから、食べ過ぎにだけは注意しましょう。
★栄養を効率よく吸収できなくなる
せっかく摂取した栄養が、食べ合わせによって吸収されにくくなってしまうケースもあります。人体に害はありませんが、できれば避けることで、栄養の吸収効率をアップできるでしょう。
- きゅうり×キャベツ
- 緑茶×ほうれん草
キャベツはビタミンCを豊富に含む食材ですが、きゅうりに含まれる成分は、その吸収を阻害することがわかっています。サラダには定番の組み合わせですが、リスクがあるという点も頭に入れておきましょう。油分を一緒に摂取すると、ビタミンCの吸収を促せますから、油分を含んだドレッシング等を活用するのがおすすめです。
ほうれん草には鉄分が多く含まれていますが、緑茶に含まれるタンニンは、体内への吸収を妨げてしまいます。ほうれん草を食べるときには、別の飲み物を選択する、もしくは摂取するタイミングを20分ほどずらすのがおすすめです。
とはいえ、こちらの食べ合わせの場合、「ビタミンCや鉄分の吸収量がゼロになる」というわけではありません。あくまでも、吸収量が減少する可能性があるだけですから、厳しく考え過ぎる必要はないでしょう。
食べ合わせも意識してより楽しい食生活を
古くから伝わる食べ合わせも、私たちにとって馴染み深い食文化の一つです。科学的根拠があるかどうかは別にして、知らないまま提供すれば、「常識外れ」と捉えられてしまう可能性もあるでしょう。食事をする際には、それぞれの食材を単体で捉えるだけではなく、組み合わせについても考慮してみてください。毎日の食事をより美味しく楽しめるだけではなく、より効率の良い栄養吸収につなげられるのではないでしょうか。
参考サイト
- その食べ合わせ、実はNG!野菜ソムリエが解説【前編】-ファンファン福岡 | 地元福岡の情報が満載
- 良い食べ合わせ、悪い食べ合わせって本当にあるの?-All About
- 食べ合わせが悪いものって本当にあるの?-ハルメクWEB|50代からの女性誌部数No.1公式サイト
- 鰻と梅干し、天ぷらとスイカ…「食べ合わせが悪い」組み合わせに科学的根拠はある?-リケラボ │ 理系の理想の働き方を考える研究所
- 身体に悪い食べ合わせは発がん性物質を産生する!?-【公式】配食のふれ愛|高齢者様向け配食サービス
- 【悪い食べ合わせ編】食材の食べ合わせ、考えたことありますか?-クックビズ総研 [飲食人材のプロによる”食”の総合メディア]