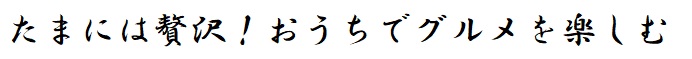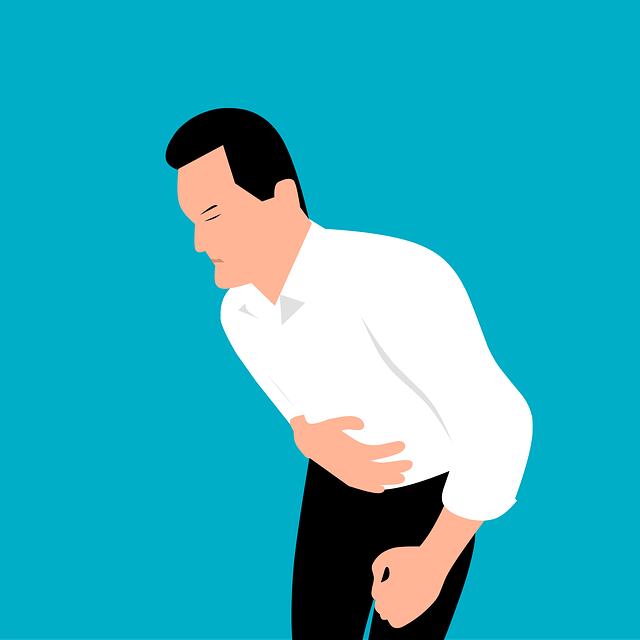私たちの日々の食事に、彩りを添えてくれる各種魚介類。せっかくですから、素材に含まれている栄養素にも注目して、摂取したいところです。
そこで今回は、身近な魚介類にどのような栄養素が含まれているのか、わかりやすく解説します。それぞれの栄養素が、私たちの健康にどのようなメリットをもたらしてくれるのかまで、じっくり掘り下げていきましょう。
魚介類に含まれる栄養素とは?
魚介類は、栄養豊富な食材です。健康維持のためにも、非常に大きな役割を担ってくれることでしょう。
とはいえ、一言で魚介類と言っても、その種類はさまざまです。種類によって、含まれる栄養素は異なるもの。自分にとって必要な栄養素を摂取するためには、どの魚介類を選択すると効果的なのか、ぜひ頭に入れておいてください。
ここでは、魚類・貝類・甲殻類の分類別に、食卓に並びやすい種類とそれぞれに含まれる栄養素の特徴について解説します。
★魚類
魚介類の中でも、特に身近なのが魚類です。夕食のメインおかずとしてはもちろん、朝食のお供として活用している方も多いのではないでしょうか。数多くの魚類の中でも、日本人に人気の魚10種について解説します。
| 真あじ(開き干し) | 100グラム当たりのたんぱく質量は20.2g。ビタミンB群やビタミンDの他、ナイアシンやリン、鉄分などミネラル類もバランスよく含む。 |
| 真いわし(生) | 100g当たりのたんぱく質量は19.2g。カルシウムや鉄の他、DHAとEPAも豊富。 |
| うなぎ(かば焼き) | 100g当たりのたんぱく質量は23.0g。ビタミンAやビタミンD、ビタミンEが豊富。DHAやEPAの他、亜鉛を含む。 |
| かつお(春獲り) | 100g当たりのたんぱく質量は25.8g。ビタミンB群やビタミンDが特に豊富。 |
| さけ(白さけ) | 100g当たりのたんぱく質量は22.3g。ビタミンB群やビタミンDの他、DHA、EPAも含まれる。 |
| 真さば(生) | 100g当たりのたんぱく質量は20.6g。DHA、EPA、ビタミンDの他、カルシウムや葉酸も含まれる。 |
| さんま(皮付き・生) | 100g当たりのたんぱく質量は18.1g。DHAやEPAが豊富。ビタミンAやビタミンDの他、カルシウムや鉄分もバランスよく含まれる。 |
| ぶり(生) | 100g当たりのたんぱく質量は21.4g。DHAやEPAが豊富。ビタミンB群やビタミンD、ビタミンEが特に豊富。 |
| きはだまぐろ(生) | 100g当たりのたんぱく質量は24.3g。鉄分やビタミンE、DHAやEPAが豊富に含まれる。 |
| 真だら(生) | 100g当たりのたんぱく質量は17.6g。ビタミンDやリン、ビタミンB12が多く含まれる。 |
★貝類
次は、貝類5種について紹介します。
| あさり(生) | 100g当たりのたんぱく質量は6.0g。カルシウムや鉄、亜鉛やカリウムが豊富。ビタミンB12も多く含まれる。 |
| かき(養殖・生) | 100g当たりのたんぱく質量は6.9g。鉄や亜鉛の他、ビタミンB12が多く含まれる。 |
| はまぐり(生) | 100g当たりのたんぱく質量は6.1g。鉄やカルシウムの他、ビタミンB12が多く含まれる。 |
| ほたてがい(生) | 100g当たりのたんぱく質量は13.5g。鉄や亜鉛など、ミネラルが豊富。 |
| さざえ(生) | 100g当たりのたんぱく質量は19.4g。ビタミンB1の他、カリウムやマグネシウムが豊富に含まれる。 |
★甲殻類
最後に紹介するのは甲殻類です。
| ブラックタイガー(養殖・生) | 100g当たりのたんぱく質量は18.4g。カルシウムやカリウムなど、ミネラルがバランスよく含まれる。 |
| ずわいかに(生) | 100g当たりのたんぱく質量は13.9g。ビタミンB12が豊富。 |
魚介類に含まれる栄養素が体にもたらすメリットは?
魚介類には、さまざまな栄養素が含まれています。とはいえ、それぞれの栄養素が体内でどのような役割を担っているのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、魚介類に含まれる代表的な栄養素について、それぞれの役割や摂取するメリットについて解説します。
★DHA
DHAとはドコサヘキサエン酸の頭文字を取ったもの。人間の身体にとって、必須の脂肪酸であるにもかかわらず、体内ではほとんど作られない栄養素です。
DHAは人間の脳や神経系に多く含まれていて、積極的に摂取することで、記憶力や言語能力の向上に効果が期待できると言われています。
この他にも、免疫機能を調整しアレルギー疾患を緩和・改善したり、高血圧や動脈硬化、脂質異常症を予防・改善したりと、健康面をサポートしてくれます。
★EPA
EPAとはエイコサペンタエン酸の頭文字を取ったもの。DHAと同じく、体内でほとんど生成されない必須脂肪酸に分類されます。
EPAの働きは、血管や血液の健康維持です。積極的に摂取することで、血液がサラサラになったり、血管年齢を若返らせたりする効果が期待できると言われています。心臓病や脳梗塞、動脈硬化予防にもなるのだそうです。
★ビタミンB群
ビタミンB群は、エネルギー生成に欠かせない栄養素です。ビタミンB群が不足すると、朝気持ち良く起きられなくなったり、疲れやすく疲れが抜けにくくなったりします。
ビタミンB群に含まれるのは、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンB12・葉酸など。
これらは体内で連携して働くため、バランスよく摂取することが大切です。魚介類に多く含まれるビタミンB12は、血液を造る際に重要な役割を果たします。
★ビタミンD
ビタミンDは、カルシウムの吸収をサポートする栄養素です。カルシウムをしっかりと摂取していても、ビタミンDが不足している状態では、スムーズに吸収されません。ビタミンDを十分に摂取することにより、骨を強くする効果が期待できます。
★ビタミンE
脂溶性の性質を持ち、高い抗酸化作用を持つことでも知られるビタミンE。若返りビタミンとしても知られています。体内で脂質が酸化してしまうのを防ぎ、動脈硬化や決戦の予防に役立ちます。
また体内の新陳代謝を促したり、外的刺激から守ったりすることで、美肌作りにも効果が期待できます。
なかなか魚料理が食べられないときの対処法
魚介類には豊富な栄養素が含まれていると知っていても、「普段の食事になかなか取り入れられていない」という方も多いのではないでしょうか。こんなときには、缶詰を活用するのがおすすめです。ツナ缶やサバ缶を活用すれば、調理の手間は最小限に、魚介類に含まれる栄養素を摂取できるでしょう。
たとえば、まぐろを使ったツナ缶を食べれば、まぐろに含まれるビタミンB群やミネラルの他、EPAやDHAも摂取可能。
サバ缶も同様です。すでに火が通っているため、調理は簡単。また、買って自宅にストックしておけば、いつでも手軽にプラスできます。
栄養豊富な魚介類を賢く食事に取り入れよう!
魚介類を日々の食事に取り入れれば、DHAやEPAの他、ビタミンB群やビタミンD、各種ミネラルなどを摂取しやすくなるでしょう。
人の健康を保つため、重要な役割を担ってくれる栄養素も多いですから、ぜひ積極的に摂取してみてください。生の魚介類から調理するのが難しい場合は、缶詰も活用するのがおすすめです。魚介類に含まれる栄養素を、効率良く摂取していきましょう。
参考サイト
- 魚介類(鮭,マグロ,ツナ缶など)のタンパク質について解説!含む量や調理法などを紹介-【森永製菓】プロテイン公式サイト
- 春のカツオでおいしく疲労回復!-大正製薬商品情報サイト
- EPAとは?-サラサラ生活向上委員会 | ニッスイ
- DHAって何?-マルハニチロ
- DHA-栄養の基本を知ろう! 栄養教養学部|栄養素カレッジ|大塚製薬
- ビタミンB群-一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所
- ビタミンDの働きと1日の摂取量-健康長寿ネット
- ビタミンE-栄養の基本を知ろう! 栄養教養学部|栄養素カレッジ|大塚製薬
- DHAやEPAたっぷりのツナ缶。DHA・EPAを効果的に摂取するための選び方-健康食品・化粧品のサントリーウエルネスオンライン[公式通販]