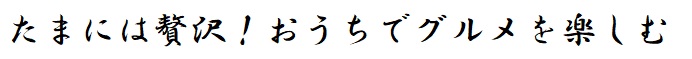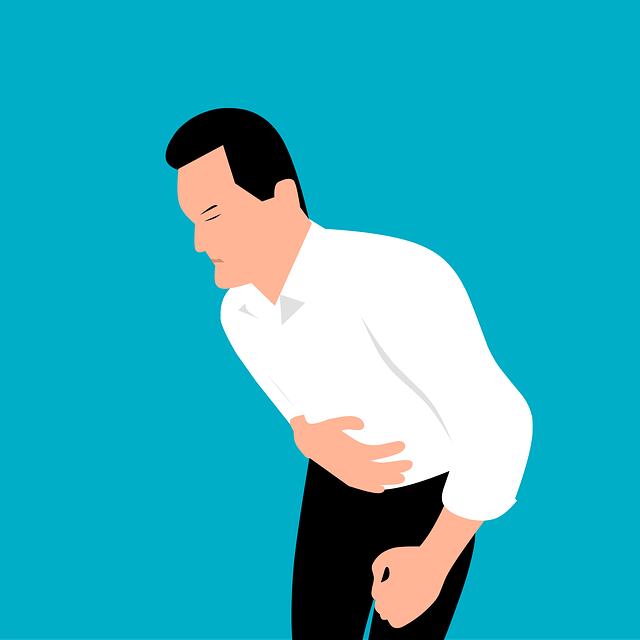
急な腹痛、嘔吐・吐き気、下痢といった症状の原因の一つが、食中毒です。食品に付着した菌やウイルスが原因で、最悪の場合には命を落としてしまうリスクもあります。
食中毒は、私たち一人一人が適切な知識を身に付け、予防対策を講じることで、防げる病気の一つです。
このコラムでは、食中毒の原因から注意したい食べ物、予防のための3原則まで、わかりやすく解説します。
食中毒の原因と種類
食中毒を引き起こす原因は、食品に付着した細菌やウイルスです。汚染された物質を摂取したことによって、下痢や腹痛、吐き気といった症状が現れます。
食中毒症状の種類や重さ、発現のタイミングは、原因となる細菌やウイルスの種類によって異なります。日本で問題になりやすい食中毒の原因菌と、症状の特徴について知っておきましょう。
★サルモネラ菌
サルモネラ菌は、食中毒の原因になりやすい細菌の一種です。乾燥に強く、熱に弱いという特徴があり、十分に加熱されていない肉や魚、卵などが原因になります。
食材がもともと菌に侵されているケースもあれば、食物を扱う人や調理器具を媒介して、別の食物へと菌が移ってしまう可能性も。
潜伏期間は12~48時間ほどで、腹痛、下痢、発熱、嘔吐だけではなく、高熱を伴うケースも目立っています。食中毒症状は比較的軽く済むケースが多いですが、小児や高齢者など、抵抗力の弱い人は特に注意が必要です。
★黄色ブドウ球菌
黄色ブドウ球菌は、私たち人間の体内からも、高確率で見つかる細菌です。健康な人からも検出される身近な菌ですが、食物が汚染されると、菌増殖の課程でエンテロトキシンという毒素を生み出してしまいます。エンテロトキシンの特徴は、乾燥だけではなく、熱や胃酸にも強いということ。たとえ食品を加熱しても、菌は除去できません。
食物が汚染される原因は、ほとんどの場合で人の手です。このため、おにぎりやサンドイッチ、お弁当など、手作り食品が原因になりやすいです。潜伏期間は平均約3時間で、吐き気や嘔吐、腹痛などが主な症状となります。
★カンピロバクター
カンピロバクターは、鶏や牛の体内に存在する細菌です。熱に弱く、また空気に触れると死滅するものの、肉の間で生き残り、加熱が充分でない場合に食中毒を引き起こします。
比較的少ない量の菌でも食中毒を引き起こしやすく、また冷蔵庫内で増殖しやすいという点にも注意が必要です。原因になりやすい食品としては、鶏肉が挙げられます。またこれ以外にも、井戸水や生野菜、ペットから感染してしまうケースもあります。
潜伏期間は2日から1週間程度と長く、下痢や発熱、吐き気や腹痛といった症状のほか、筋肉痛が出るケースもあります。
★ノロウイルス
感染症で有名なウイルスですが、汚染された食物を摂取すれば食中毒の原因になります。非常に感染力が強く、食物以外にもさまざまなルートで感染する可能性があるでしょう。
ノロウイルスの原因になりやすい食物は、カキなどの二枚貝です。充分に加熱しないまま摂取することで、吐き気や腹痛、ひどい下痢といった症状が現れます。
実際には、二枚貝が原因となって食中毒を引き起こすケースよりも、人の手指に付着したウイルスがきっかけになるケースが多いようです。ノロウイルスが付着した手で食材を触れば、あらゆるものが食中毒の原因になるでしょう。
潜伏期間は1~2日ほど。また、85度以上で1分間以上加熱すれば、原因ウイルスを死滅させられます。
★腸管出血性大腸菌
食中毒の中でも、特に重篤な症状を引き起こしやすいのが腸管出血性大腸菌です。O157やO111といった種類があります。
もともと動物の腸内に存在する菌で、十分に加熱されていない肉類が原因になるケースが多く見られます。
ただし、家庭内で1人感染者が出れば、患者や看病する人の手指を介して、二次感染を引き起こす可能性もあるでしょう。
潜伏期間は12時間から3日ほどで、非常に激しい腹痛や水溶性の下痢といった症状が現れます。症状が悪化すれば、血便や重症合併症を引き起こすリスクもあります。
★その他
また、これら以外にも、キノコ類に含まれる自然毒や、魚類に寄生する虫(アニキサス)等が原因で食中毒が発生する可能性も。食中毒は、あらゆる食材、あらゆる状況で起こりうるという点を、しっかりと頭に入れておきましょう。
食中毒を起こしやすい食べ物
食中毒は、さまざまな食べ物が原因で引き起こされる病気です。どんな食べ物も、保管方法や調理方法によって、感染源になり得るという点を頭に入れておきましょう。
中でも特に注意したいのは、以下のような食べ物です。
- 十分に加熱されていない肉類や卵
- 生の魚介類
- 生野菜
- 手作りのおにぎりやサンドイッチ、お弁当
肉や卵、魚介類は、中心部までしっかりと火を通すことが大切です。生野菜やお弁当類については、食物そのものを完全に避けるのは難しいでしょう。ただし、「食中毒が発生するリスクが高い」と知っていれば、相応の対策もとれるはずです。食中毒のリスクを甘く見ないようにしてください。
食中毒予防の3原則
食中毒は、何よりも予防が大切です。自身と大切な家族の命を守るためには、食中毒予防の3原則を意識しながら生活してみてください。
【食中毒予防の3原則】
- 付けない
- 増やさない
- やっつける
食中毒の原因となる細菌やウイルスを、人間の社会から完全に消し去ることは難しいでしょう。だからこそ、まずは人の口に入る食物に「付けない」ための取り組みが重要です。菌はゼロの状態であれば、繁殖しません。そのためにも、調理前の手指の洗浄・消毒は徹底しましょう。
調理器具も同様です。生の肉や魚を扱ったあとや、食事を始める前にも、しっかりと手指を洗浄・消毒してください。「生肉→生野菜」ではなく、「生野菜→生肉」という風に、調理の順序に工夫するのも効果的です。
菌やウイルスを付けないのが理想ですが、なかなか難しいこともあるでしょう。こんなときには、「増やさない」ための取り組みが重要な意味を持ちます。夏場に食中毒リスクが高まるのは、高温多湿な環境になるためです。多くの細菌は高温多湿な環境を好み、あっという間に増えていきます。爆発的な細菌増加を防ぐためには、低温での保存を心掛けるのが一番です。購入後に素早く冷蔵庫にしまうのはもちろん、調理中・調理後の状態にも気を配ってください。
食中毒の原因となる菌やウイルスの多くは、熱に弱いという特性を持っています。このため、中心部までしっかりと加熱すれば、食中毒リスクを低下できるでしょう。加熱の目安は、食品の中心部が75℃で1分以上です。食中毒リスクが高い環境下においては、肉や魚はもちろん、野菜類も加熱して食べるのがおすすめです。
これら3つの原則を意識していれば、食中毒リスクはかなり低減できるでしょう。ぜひ意識してみてください。
食中毒について正しい知識を身に付けよう
目の前にある食材が、食中毒菌に汚染されているのかどうか、見た目や匂いから判断するのは不可能です。だからこそ重要なのは、適切な知識を身に付け、より確実に予防することです。
また、万が一食中毒になってしまったときには、素早く医師の診察を受けましょう。悪化する症状を放置すれば、最悪の場合、死に至るケースもあります。できるだけ早い段階で適切な処置を受けることが、非常に重要なポイントと言えるでしょう。
参考サイト
- 食中毒予防の原則と6つのポイント-政府広報オンライン あしたの暮らしをわかりやすく
- 食中毒-厚生労働省
- 食中毒の原因と種類-農林水産省
- サルモネラ食中毒(食中毒菌などの話)-公益社団法人日本食品衛生協会
- 黄色ブドウ球菌-「食品衛生の窓」東京都福祉保健局
- 食中毒(黄色ブドウ球菌)とは? -サラヤ株式会社 家庭用製品情報
- カンピロバクター食中毒の症状や特徴、予防方法について-食品衛生の管理なら 株式会社町田予防衛生研究所
- ノロウイルス食中毒(食中毒菌などの話)-公益社団法人日本食品衛生協会
- 食中毒(腸管出血性大腸菌O157)とは? -サラヤ株式会社 家庭用製品情報
- 食中毒になりやすい食品は?テイクアウトやデリバリーの注意点と食中毒予防3原則-お薬のことならホウライ 信頼をかたちに、明日の医療を考える。
- 「食中毒について」:みんなの医療ガイド-公益社団法人全日本病院協会